- マシナリーお役立ちNAVI
- 工作機械を学ぶ
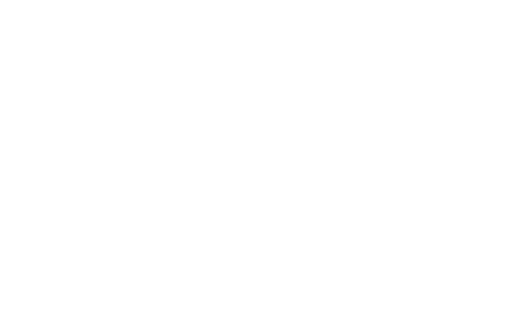
モノづくり現場の人材確保
-多様性を活かした
雇用促進のポイント-
公開日:2025.07.22

工場勤務と聞くと、重労働や単調な作業の繰り返しといったマイナスイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。しかし、近年の技術革新やオートメーション化の進展により、製造現場の労働環境は大きく変化しています。
そのようななか、製造業では人材確保や雇用促進が重要な課題となっています。これまで工場勤務に馴染みのなかった方や、幅広い年代・多様なバックグラウンドを持つ人々も、ものづくりの現場で活躍するケースが増えています。
本記事では、製造業における人材確保や雇用促進の現状と課題について解説し、多様な人材が働きやすい環境づくりのポイントや、企業が取り組むべき施策について紹介します。
工場で働くメリット
最初に、工場勤務を選ぶメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、工場で働くことのポジティブな側面をご紹介します。
地方や地元で働ける
工場は地方にも多く立地しており、地元の人材を積極的に採用する傾向があります。地域に根ざした企業では、地元の学校から直接採用するケースも少なくありません。
地元で働きたい、家族のそばで暮らしたいという方にとって、工場勤務には大きなメリットがあるといえるでしょう。
専門的な知識が身につき、
長期的なキャリア形成ができる
工場で働くことで、専門的な技術や知識を身につけられるのも製造業に携わる大きな魅力です。生産管理や品質管理、設備のメンテナンスなど、モノづくりに直結する実践的なスキルを習得できます。
他社でも通用するようなスキルセットが身につけば、長期的な視点でキャリアアップも望めます。
技術進化で、未経験でも
働きやすくなっている
IoTやAIの活用により製造工程の自動化が進み、熟練した職人の技術がなくても高い品質の製品が作れるようになっています。作業手順もマニュアル化されていることが多く、製造業未経験者に対する門戸が広がっているといえるでしょう。
仕事とプライベートを
両立させやすい
工場勤務では、シフト制を導入している企業が多いため、勤務時間が明確に定められています。そのため、プライベートの予定を立てやすく、仕事と生活の両立が図りやすいでしょう。また、近年の製造現場では「脱属人化」を進める企業も多く、誰が担当しても一定の品質を保てるような仕組みづくりに努めています。
工場で働くことの
デメリットは?
工場で働くことには多くのメリットがありますが、すべてが理想的というわけではありません。ここでは、工場勤務のデメリットについて解説します。
仕事によっては単調で
つらいと感じることも
工場の仕事はライン生産方式が主流であるため、同じ作業の繰り返しになることもあります。単純作業が苦手な方にとっては、仕事に対して意欲がわかなくなる場合もあるでしょう。ただし、モノづくりが好きでコツコツと作業を続けることに喜びを感じる方もいるため、向き不向きがあります。
また、将来的には単調な仕事は自動化技術の進歩により徐々に減っていくと考えられます。単純作業は機械に任せ、人はより創造的な仕事に携わる機会が増えていくでしょう。
今後は発想力やコミュニケーション能力、論理的思考力といったスキルがより重視されるようになることが予想されます。
仕事に慣れるまでは大変
工場の仕事には、専門的な知識や技術が必要とされる場合があります。例えば、電子部品の組み立てでは基板の種類や部品の名称、はんだ付けの方法など、覚えることが多岐にわたります。
また、機械化・自動化が進んでいるとはいえ、まだまだ人の手による作業も多く、一定の熟練度が求められることもあります。そのため、仕事に慣れるまでは大変に感じるかもしれません。
一方で、こうして身につけたスキルや技術は、自身のキャリアの強みになります。しっかりとしたスキルセットが身につけば、転職やキャリアアップの際にも有利になるでしょう。
雇用確保のために工場が
できること
日本の製造業は、少子高齢化による労働力不足や、熟練技術者の引退など、さまざまな課題を抱えています。この状況を打開するためには、性別や年齢を問わず、若い世代からシニア世代まで幅広い人材の雇用を促進することが重要です。
企業にとっては、多様な人材が活躍できる環境を整えることが求められています。最後に、企業側の視点から製造業における幅広い人材の雇用促進について考えてみましょう。
人に頼らざるを得ない部分を精査
製造業では自動化が進む一方で、人の手に頼らざるを得ない工程も依然として存在します。
例えば、細かな部品の取り付けや品質チェックなどは、人の目と手が不可欠です。こうした工程を精査し、経験豊富なベテラン社員の知見を言語化・マニュアル化することで、生産性の向上とともに、幅広い人材が活躍できる環境づくりが可能になります。
年齢や性別を問わず、多様な人材が働きやすい職場改善にもつながるでしょう。
製造環境の改善
幅広い人材が製造現場で活躍するためには、誰もが働きやすい環境づくりが欠かせません。
例えば、重量物の運搬や油汚れのある作業は、体力や経験に関わらず負担となる場合があります。こうした課題を解決するため、設備投資によって工作機械や製造ロボットを導入する企業が増えています。
また、生産用機械の省エネ化も進んでおり、環境負荷の低い持続可能なモノづくりの実現に取り組む企業もあります。さまざまな取り組みを通じて、職場環境や企業イメージの改善を進めることで、性別や年齢を問わず多様な人材の雇用を促進することが重要です。
専門的な技術の再現性を向上
製造業では、熟練技術者の引退にともない、専門的な技術の継承が課題となっています。この問題を解決するには、技術のデジタル化や自動化の推進が不可欠です。例えば、金型の設計や加工は従来、熟練技術者の経験や勘に頼る部分が大きいとされてきました。しかし、最新のマシニングセンタなどを導入し、設計データをもとに高精度な加工ができるようになれば、専門的な技術の再現性が高まります。
こうした取り組みにより、性別や年齢、経験の有無を問わず、誰もが高度な仕事に挑戦できる環境が整い、幅広い人材の雇用促進につながります。技術のデジタル化と自動化は、多様な人材が活躍できる製造現場づくりに大きく貢献するといえるでしょう。
工場勤務の現場は、技術革新やオートメーション化の進展によって大きく変化し、多様な人材が活躍できる環境が整いつつあります。今後は、従来のイメージにとらわれず、誰もが働きやすい職場づくりや技術の継承・発展に積極的に取り組むことが、製造業の持続的な成長につながります。
多様な人材が力を発揮できる製造現場を目指して、企業と働く人双方の意識改革が求められています。
女性が活躍する現場の声はこちら SPEEDIOを扱う女性の声

●瑞浪精機株式会社様

●株式会社サクラテック様
-
文:小林悠樹
1988年生まれ。一橋大学卒業後、食品メーカーへ入社。営業職を経験したのち、2017年にフリーライターへ転身。企業への取材記事、通信大手のオウンドメディアなどをはじめ、幅広いコンテンツを手がけています。
-
編集:株式会社イージーゴー
WEBコンテンツ、紙媒体、動画等の企画制作を行う編集制作事務所です。ライターコミュニティ「ライター研究所」も運営しています。
https://eggo.jp/
- 時短加工したい
- 加工時間を短縮して高効率&生産性アップ
- ブラザーホーム
- 製品情報
- 工作機械
- マシナリーお役立ちNAVI
- モノづくり現場の人材確保









![[新しいウィンドウ]](/-/media/cojp/product/machine/speedio-navi/img/articles/out-link.ashx)



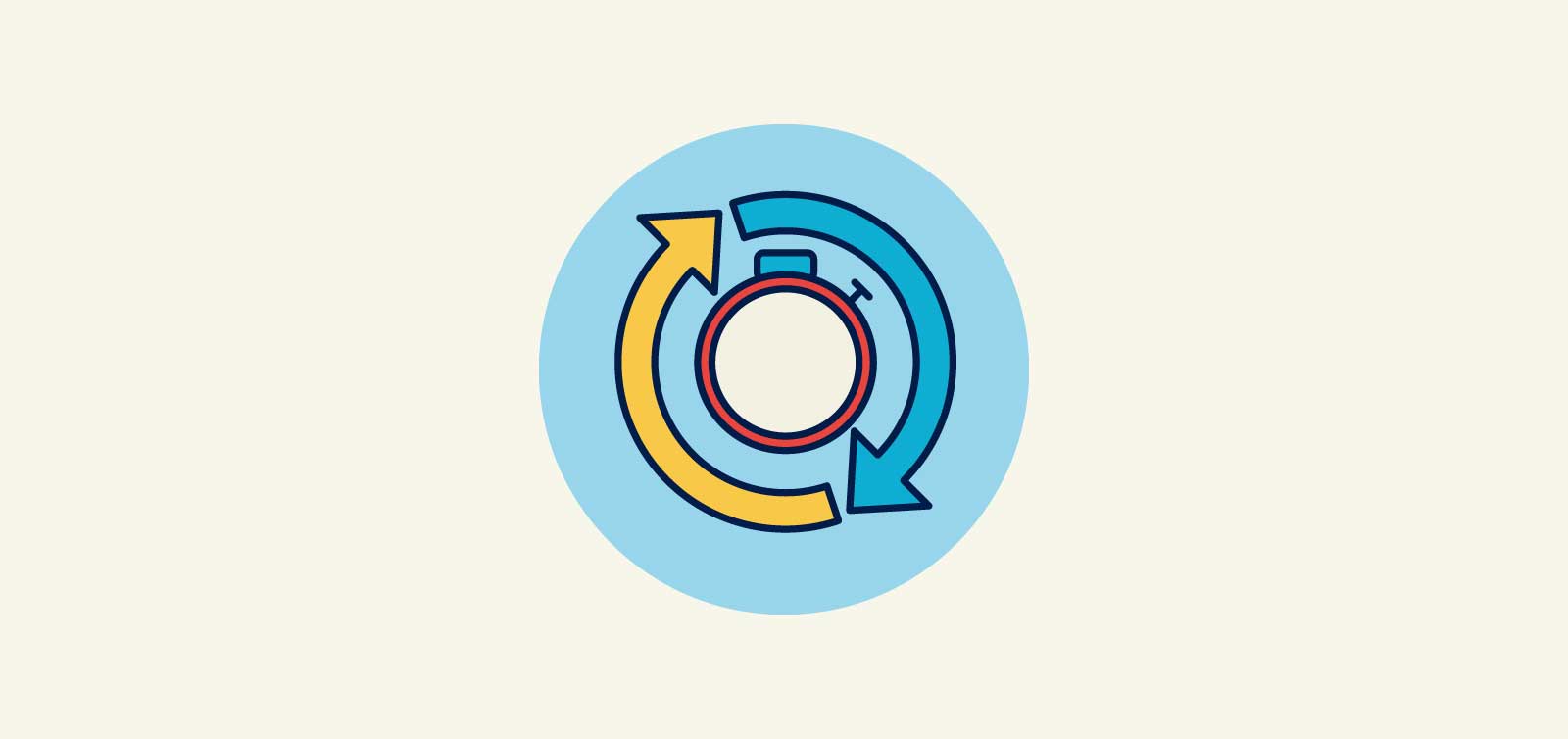

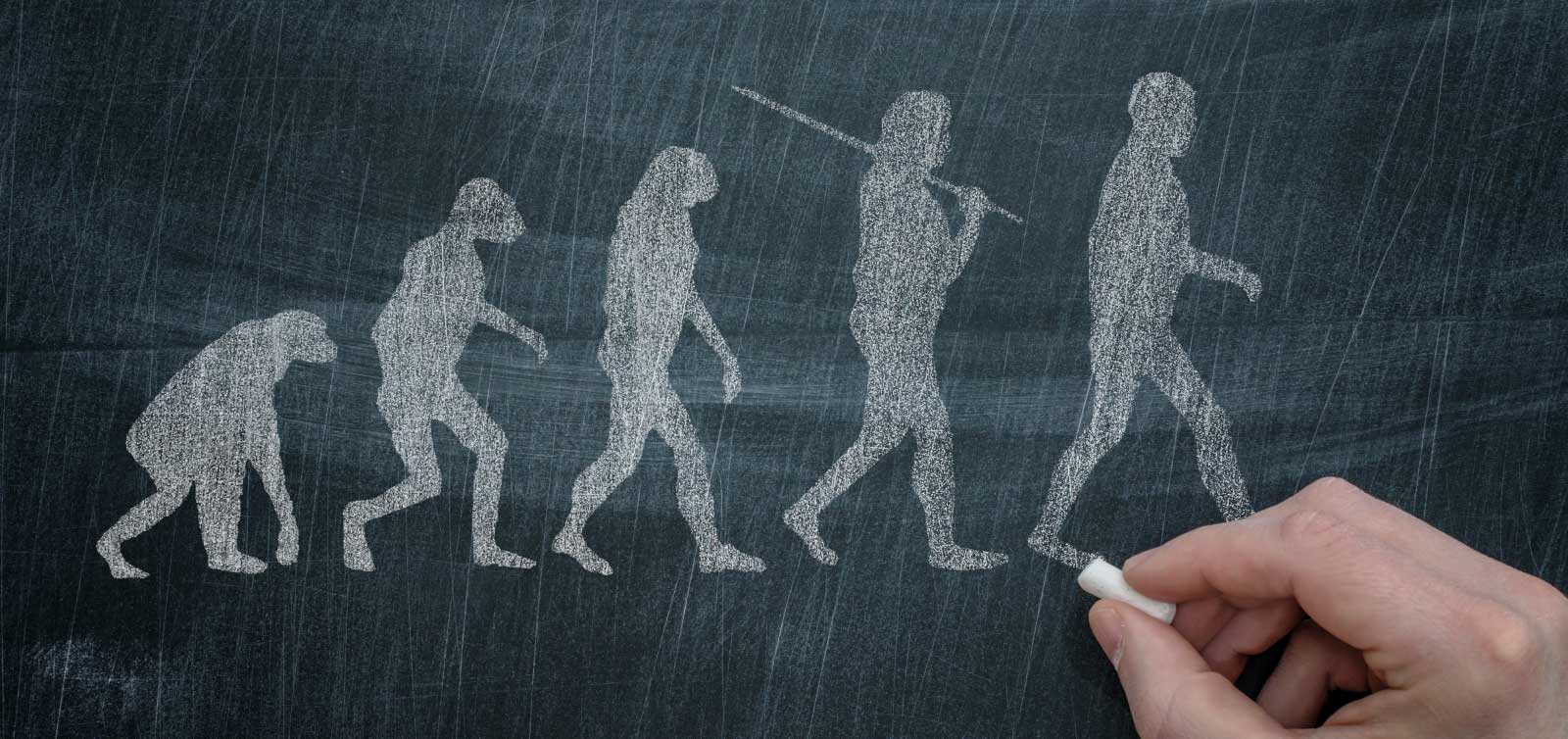
 Facebook
Facebook X
X LINE
LINE